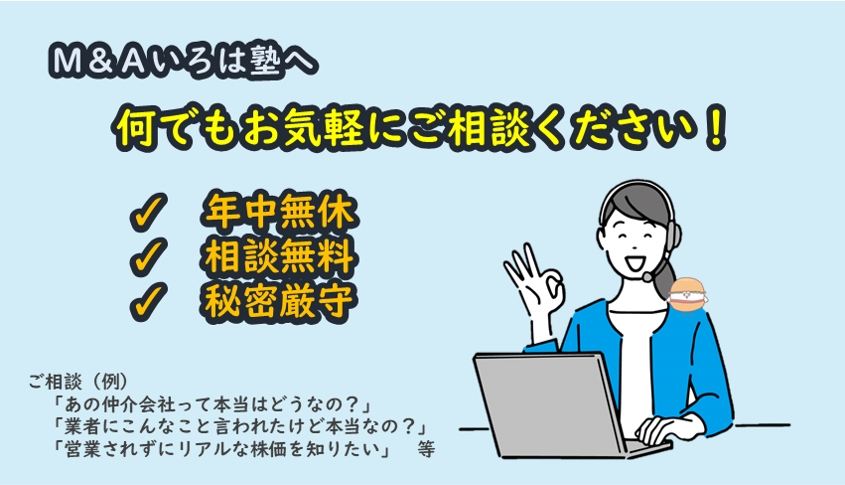お悩み社長
お悩み社長
これは、結論からいうと実際あると思います。
公的機関である「事業承継・引継ぎ支援センター」というのは全国にあり、その運営方針は地域によって変わるところもあるので一概には言えませんが、様々な事情によって、特定の業者が紹介されているということが起きます。
中には、「それって癒着じゃない?」って思うような事例もあります。
今回はM&Aと癒着、というテーマで考えてみたいと思います。
基本的に、紹介者や業者側が癒着をし始めると、実際に会社や事業を売却しようとしている売主にとってはデメリットしかない(払わなくていいコストを払わされる)オチにもなる可能性が高いので、売手の立場であればこの辺の関係性や実態は知っておきたいところです。
事業承継・引継ぎ支援センターで業者を紹介してもらうケース
事業承継・引継ぎ支援センターとは、親族内への承継や第三者承継等について相談ができる国が設置する公的相談窓口です。
各都道府県に1カ所は設置されており、大体は県庁所在地の商工会議所の一室にあったりします。
当然、公的機関なので無料です。
単に相談するだけならそれだけですが、実際は「後継ぎがいない」という問題を抱えている相談者もいるので、誰か引き継いでくれる会社はないかという話の流れで、引継ぎ支援センターに買手や業者を紹介してもらうこともあります。
M&A業者の数はとっても多いので、訳の分からない手紙をいきなりよこしてくる怪しいM&A業者や、紹介料目当てのブローカーチックな人に相談したり、紹介してもらうよりも安心感はありますからね。
引継ぎ支援センターは、買手となる会社が「こういう希望に合う譲渡案件はないか」と相談に来ることもあるのでそういった直接ニーズを聞いている買手との引き合わせをするか、登録しているM&A業者(これはM&A支援機関制度への登録とは別の引継ぎ支援センターへの登録を指します)を紹介することになります。
ここでM&A業者を紹介する場合、筆者が知る限り、大体こういう流れで業者がチョイスされます。
・引継ぎセンターと業者間で共有しているプラットフォーム*上で限定的な情報が公開され、その譲渡案件に対して紹介できそうな買手がいるという業者がオファーをして、引継ぎセンター経由で紹介するケース
・上記のようなケースで複数の業者からのオファーがあった場合、コンペ形式で各業者が売主と会話し、売主がその中から選ぶケース
・引継ぎセンター担当者から業者への直接的な持ち掛けをして業者が応じるケース
*このプラットフォームというのは、不動産でいうところのレインズに近いようなもので、全国の引継ぎ支援センターで「業者募集中」というステータスになった譲渡案件を、引継ぎ支援センターと登録しているM&A業者だけが見れる(一般には見れないし、譲渡企業名はプラットフォーム内でも伏せている)仕組みです。これを見て、「買手紹介できます!」という場合はオファーします。
ここでの問題は、こういった業者の選ばれ方が公明正大に行われているか、売主にとって不利にならないか、という点です。
実際、特定のM&A業者と癒着していることはある?
筆者が業者の立場でこの問題について考えてみると、こういうことが実際あります。
・実際は存在する譲渡相談がプラットフォームに登録されていない
・掲載されている譲渡案件にオファーしても担当引継ぎ支援センターが反応しない
・引継ぎ支援センターの裁量で業者を絞る
・引継ぎ支援センターの担当者が銀行OBで、古巣の銀行に案件を流す など
引継ぎ支援センターが、相談を受けた案件を全部漏れなくプラットフォームに登録しているわけではありません。
案件としてスタートするにはまだ売主の気持ちが固まっていない、とかそういった案件もあるとは思いますが、引継ぎ支援センターによっては、明らかに優良な案件は色々なM&A業者も確認できるプラットフォームには載せずに特定業者にしか公開していないと思われる動きもあります。
また、引継ぎ支援センターの担当者は、士業の専門家だけではなく、銀行のOBなども結構在籍しており、そのOBが優良な案件を古巣の銀行に流している、という話も聞いています。
引継ぎ支援センターにとっても過去やり取りのある業者や知っている業者に任せたい、という気持ちがあるのは分かりますが、引継ぎ支援センター担当者と馬が合うからといって売主も馬が合うとは限りませんし、大手仲介会社だけ絞って売主に紹介するということをすれば、どの仲介会社を選んでも最低報酬額が高額なところしかない、ということにもなりかねません。
つまり、売主にとっては不利益を被ることがあるってことです。
引継ぎ支援センター担当者は色々なM&A業者と接するので、あそこの業者は良いとか悪いとかの判断軸はあるのかもしれませんが、これも網羅的であるとも限らないので、結局のところ、売主は引継ぎ支援センター担当者の主観も入った業者を押し付けられるリスクはあると思います。
あれば大問題ですが、引継ぎ支援センター担当者が業者からバックマージンを貰うとか、優良案件を流した見返りが何かあるのであれば、社会問題化するかもしれませんね。
仕事としてやっているM&A紹介者やブローカーと言われる人々はバックマージン欲しさに、敢えて、手数料の高いM&A業者を紹介したくなるバイアスがかかるので、売主がこういう人とは関わるのは得策でないのはいうまでもありませんが、引継ぎ支援センターについても公的機関だから何のバイアスもかかっていないだろうと思うのは早計です。
引継ぎ支援センター担当者も、心の底から「後継者のいない中小零細企業を救いたい!」と思って参画している人ばかりではなく、本業が少し暇になったので割のいいバイト感覚でやってみるか、という人も実際いますので・・・。
紹介者側の癒着は売主にとって損しかない
売主というのは、最初から結構不安定な立場にあります。
この人なら信用できそうかな、と思った人がどこかと癒着しており、払わなくていい手数料を払わされる羽目になった、まんまと騙されたということが起こるからです。
不動産業界では、売主が不利益を被る可能性のあるこうした情報操作が違法になることもありますが、M&A業界は法整備も整っていないので、まだまだ何でも起こり得ます。
じゃあ、そういう想定外の事態が起きないためには何をしたらいいでしょうか。
それはこういう業界構造について理解することです。
引継ぎ支援センター全体が癒着構造があり問題だとは筆者も全く思っていません(むしろすごく親切な担当者もたくさんいます)が、仕組みとして緩いところがあれば当然変な使い方をする人が出てくるという見方は常に持っておく方が安全です。
もし、紹介されたM&A業者が手数料の高額な仲介会社や銀行ばかりだったとしても、一般的なM&A業者の最低報酬水準分布の資料(M&A支援機関登録制度実績報告等についてなど)知っていれば、「あれ、これ紹介されてる業者偏ってない?」って思うはずです。
筆者はできるだけこういう業界構造について伝えたくてこのブログを書いていますが、一つの意見として参考にしていただき、M&Aを進める上で何か気になることが起きた時に「あれ、あのブログになんか近いようなこと書いてあったな」と思い出していただければ嬉しい限りです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
内容について気になること、筆者へのご相談があれば下のお問合せフォームよりお問合せ下さい。