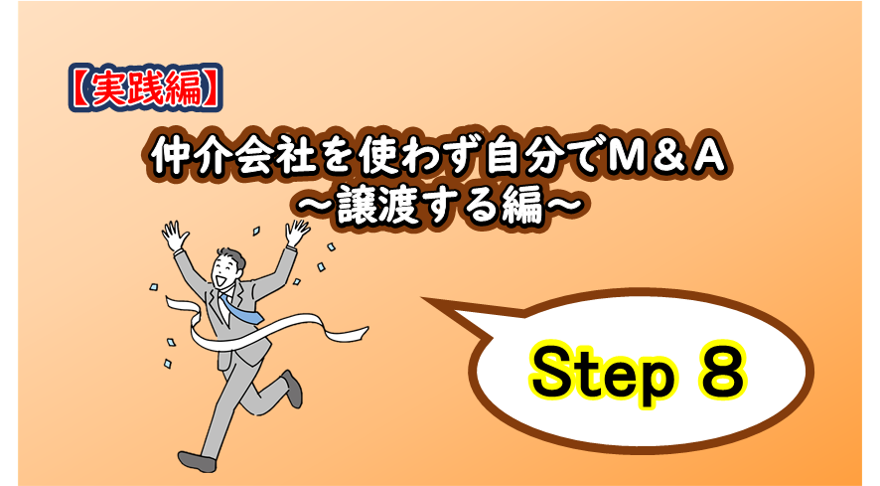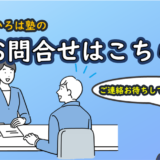前回の「【実践編⑦】仲介会社を使わず自分でM&A(最終契約書を結ぶ編)」からの続きです。
前回記事を確認したい方はこちらからどうぞ。
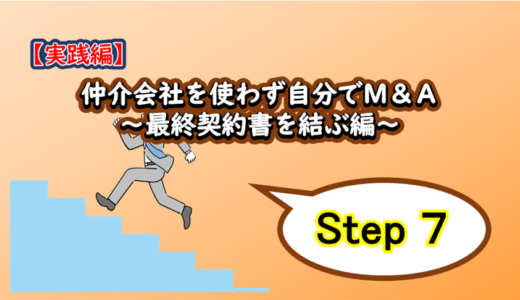 【実践編⑦】仲介会社を使わず自分でM&A(最終契約書を結ぶ編)
【実践編⑦】仲介会社を使わず自分でM&A(最終契約書を結ぶ編)
今回の実践編では、「サクッと売りたい」という方向けに自分で会社・事業を売る方法をできるだけ分かりやすくお伝えしております。
なお、毎度の留意点ではありますが、あくまで一般的な例でお伝えしますこと、及び、ご自身で進める場合にはM&Aに関するトラブル等について当サイトでは一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。
今回説明するのは、M&Aのこの部分の話です。
実践編でお伝えしているこちらのシリーズは今回で最終回で、いよいよM&Aを実行する場面です。
基本的には、締結した最終契約書の通りに取引をするだけなのであまり難しいことは無いですが、手続き的な内容と従業員への説明の仕方などを解説していきます。
売手としてはお金をもらうのも大事ですが、譲渡した会社や事業が今後もきちんと運営できることも非常に重要なので、是非最後までお読みください。
それではいきましょう!
譲渡に際して行う手続き
M&Aを行う際には、取引に応じた事務手続きが必要となります。
仲介会社を使う場合には、仲介会社が用意した書類(クロージングパッケージ)にポンポンとハンコを押していけば済むのですが、自分でM&Aを行う場合には自分と買手で用意しないといけません。
株式譲渡を行う際に必要な会社法上の手続きは司法書士が対応しますので、もし会社設立などでお世話になった先生がいれば相談して資料も作ってもらうことをおすすめします。
一般的に株式譲渡で売手が事前にやることはこんな感じです。
譲渡の後は、買手が株主の名義書き換えや、臨時株主総会で役員退任・新任役員の選任・役員報酬の決定・役員退職金払出等の決議を行いますし、代表者変更等の登記に必要な書類を用意しますので、ここには売手としてもきちんと協力しましょう。
ちなみに事業譲渡の場合は、株主総会の特別決議を開き事業譲渡契約の承認を行うこと、譲渡する資産や契約等の名義切り替え等を行います。
株式譲渡と異なり事業譲渡はこの名義切り替えが大変です。不動産であれば所有権移転登記が必要になりますし、車両の名義変更や、各種契約の契約書を売手から買手に変更することも必要になります。従業員も全員雇用契約を巻き直しします。
やらないといけないことは案件や最終契約書で取り決めしている内容によって異なりますので、実際これらを自分で調べて行うのはしんどいと思います。買手がこの辺に詳しければお任せしてしまうのも良いかもしれません。
これらを全てクリアして、ようやくM&Aの譲渡手続きが完了した、ということになります。
従業員や取引先への説明
さて、M&Aの話は今まで従業員や取引先に隠していた方が多いと思いますが、この段階になると開示しないといけません。
伝えるタイミングとしては、事業譲渡の場合は従業員毎に転籍が必要となりますので譲渡の直前、株式譲渡の場合は譲渡の翌日などに従業員に伝えることが多いようです。
それではどんな話をしたらよいのでしょう?
大体はこんな内容を伝えます。
買手との話の中で、M&A後も当面は従業員に同じような仕事をしてもらい、給与面も据え置きにするということが多いので、この辺はそこまで混乱が起こることは無いと思います。
大抵の従業員はM&A後のイメージを具体的に想像できるわけではないので、ポカーンという感じですが、たまに鋭い従業員もいたりします。
ここではとにかく不安を抱かせないように真摯に対応しましょう。暴れそうな従業員がいたり、明白に目をかけているような従業員がいる場合には全体に伝える前に個別に話をしても良いでしょう。
なお、売手としては、これからは自分の会社ではなくなるわけのなので、今後何をするかという点については買手の同意を得ずに想像で伝えるのはやめましょうね。
また、M&Aで大金が入ったからといって従業員に配ろうとする売手もいますが、これは買手が嫌がる可能性もあるので事前に買手に相談しましょう。配り方が不公平だと不満が発生する原因にもなりかねませんし、これからは買手がその従業員をコントロールしないといけないのに、売手が前の社長を慕っているという環境は買手にとってはやりづらいからです。
従業員の説明の仕方や注意点についてはこちらの記事もご参考ください。
 「M&A後の説明をミスして大量離職発生!?」売主の責任と従業員説明のポイントを解説
「M&A後の説明をミスして大量離職発生!?」売主の責任と従業員説明のポイントを解説
取引先については、M&A後もきちんと取引が継続できるよう注意しながら伝えましょう。
実際面談して事情を説明した方がよい取引先もいるでしょうし、お手紙でも問題ない取引先もいるでしょう。M&Aの話はこういう風に伝えないといけない、というきまりは無いので、今までの関係性を考えて対応します。
「絶対言わないといけないの?」という方もたまにいらっしゃいますが、事業譲渡の場合は基本取引契約書の名義も変わるのでM&Aの話を言わないわけにはいかないと思います。株式譲渡の場合は会社名はそのままなので、単純に代表者変更のお手紙だけを送っている人もいたりしますが、取引を継続するのであればきちんと伝えた方が良い場合もあります。
なお、隠したとしても会社の謄本は誰でも取得できますし、創業一族でもない人がいきなり代表取締役になっていたとしたら「M&Aして親会社から人が来たのかな」と勘ぐるものなので、後から水臭いと言われないように進められるとよいかと思います。
ちなみに従業員への説明もそうですが、関係者への情報開示は売手の責任を持って行います。そして開示する内容(話す内容)は全て買手と逐一相談・報告をしながら進めるようにしてください。
譲渡した後に気を付けること
譲渡した後も当面の間は事業運営で大きな問題が起きないように売手も気を付けて買手のフォローに回りましょう。
譲渡直後に問題が発生すると、M&Aが原因で発生した問題とみなされることも少なくないので、責任問題に発展しないように売手も注意すべきです。今時点で問題が発生していなくても、「この火種を放置しておいたら絶対に問題になるな」という感覚は売手の長年の経営者の勘であると思いますので、その感覚的な部分も買手にきちんと伝えてあげましょう。
また、売手は納税についても注意しましょう。
M&Aの売却代金は、譲渡日に全額口座に振り込まれます。
金融所得であれば現在20.315%の税金の支払義務が発生しますが、それも全部口座に振り込まれますので、間違って使ってしまうなんてことが内容に注意しておく必要があります。
なので、納税用の資金は分けておくと良いですね。
M&Aは大金が動くので、税務調査が入りやすいと言われていたりもします。
問題無く取引が完了した、と思っていても、譲渡直前に株主間で売買していた買い集め分が贈与扱いになってしまったり、役員退職金が否認されて追徴を食らったりと、、場合によっては全然笑えない額になるので、顧問税理士とも相談した上で、リスク度合いを事前に理解しておくと良いでしょう。
いかがでしたでしょうか?
適法に取引を成立させて、果たすべき義務をきちんと果たして、晴れて自由の身です。
新しい体制になった会社・事業の将来に期待しながら、自分の人生についても新しい一歩を踏み出しましょう!
ちなみに筆者がお手伝いした売手オーナーの中には、
「会社を売却して暇になってしまったので、今度は自分が買手になって今までとは全く違う事業を始めたい!」
と、新たな事業意欲を燃やされる方もいらっしゃいます。
自分の会社や事業に心血を注いでいた方であればあるほど、何か次に情熱を注ぎたいと思うものなのかもしれませんし、今まで悩みの種であった人繰りも実は自分の人生を充実させるために必要なものだったことに気づくものかもしれません。
その時は、今度は立場が逆になると思いますが、M&Aの買手として今回お伝えしたような手順で進めていただければと思います(笑)
最後までお読みいただきありがとうございました!