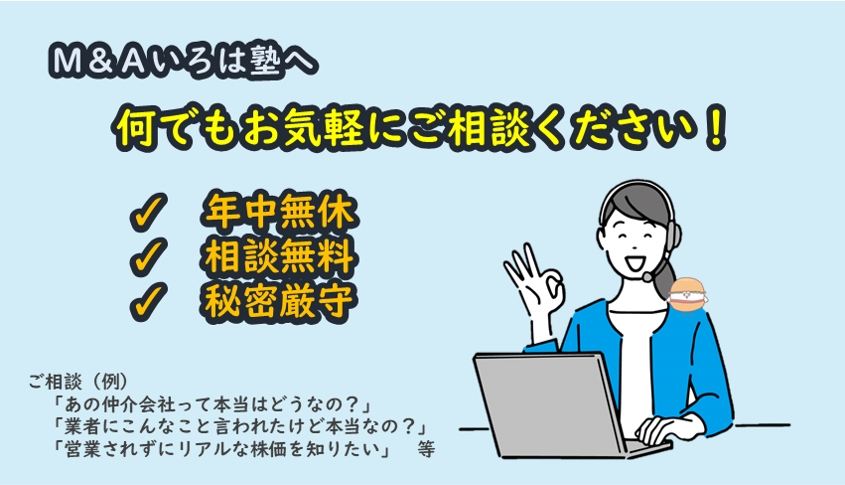お悩み社長
お悩み社長
昨今、「M&Aの買手が売手を騙した」「M&A仲介会社がそれに加担した」といったニュースも多いですが、事前に詐欺の予兆のようなものは確認できないか、と思う方もいると思います。
詐欺師が自分で「詐欺師です」なんていうわけないので、警戒していないと危ないのは事実。
でも、全部疑ったら疑ったで疑心暗鬼になってしまいM&Aなんて踏み切れない。
もうM&A検討するのやめようか、とも思ってしまいますよね(笑)
M&A業界では「危ない買手の情報は業者間でシェアしよう!」という取り組みも始まっていますが、これも不十分です。詐欺師はいくらでも自分を偽って近づいてきますので防ぎきれないです。
でも、手口を抑えておけばある程度防ぎようがありますし、長年M&A仲介をしているとその違和感に気付ける人もいます。
筆者も、成約を手助けはしていませんが詐欺師のような買手とやり取りしたことが何度もあります。
言葉で説明しづらいですが、彼らが醸し出す違和感は独特なものがあるので、警戒度を上げて深堀していけば怪しさに気付くものですが、あんまり経験の無い人が直接やり取りすると気付かないような気もしています。
今回は、方法論として「M&A詐欺師はどういうところで見抜けるのか」「どういう対策が有効か」について解説していきたいと思います。
怪しい買手だと気付くポイント
筆者が過去やり取りしたことのある怪しい買手の中には、実際にM&A詐欺を行った某R社(L社?)なども含まれます。
筆者の感覚的にですが、詐欺を行う会社の中でも結構能力差があるのが印象的で、地面師級に作り込んでくるレベルもいれば、模倣犯レベルのものもいます。ここではその特徴を挙げてみます。
もし、読者の方でこのような特徴を持つ買手とまさにやり取りしている最中、ということであれば、一旦交渉を止めて、考え直すきっかけにしていただければと思います。
メールアドレスがフリーアドレス
やり取りしているメールアドレスがフリーアドレスという買手は気にした方がよいです。
フリーアドレスとは、「@gmail.com」とか「@yahoo.co.jp」といった誰でも簡易に、すぐ取得できるアドレスであり、足がつきにくいのが特徴です。
詐欺師はいつでも逃げることを考えているので、できるだけ素性を隠したい心理が働きます。会社のドメイン名すら明かさない(もしくは、買手企業すら偽っているためドメインを管理する権限がないのでは?)といったことも怪しいなと思うポイントです。
場合によって、「会社に内緒でM&Aを検討しているから」という買手もいるかもしれませんが、M&Aを検討している事実は、買手にとってはそこまで隠し通すほどの情報ではないので、実務的にはフリーアドレスを使ってくる買手は多くはないです。
あと、メールアドレスは「tanaka@」とかなのに、山田と名乗ってくるような人も怪しいです。
Web検索すると黒い噂が検索で出てくる
Web魚拓ともいいますが、「〇〇(やり取りしている相手の名前・社名)+詐欺(事件)」などで検索すると、たまに黒い噂が出てくることもあります。
犯罪心理学では「犯罪の専門化」という概念がありますが、これは、犯罪者は過去に成功した手口や経験に基づいて、同じタイプの犯罪を繰り返す傾向があるというものです。特定の犯罪に慣れることで、「心理的障壁」が下がり再犯に繋がるとか、犯罪にもスキルがあり経験を積むと成功率が上がる、といったことが原因だと言われていますが、要は、「詐欺をする者は過去にも詐欺をしている可能性がある」ということです。
偽名のケースもあるので、苗字だけ・名前だけ、あるいは他に推測できる名前を使って、「詐欺」「M&A」など関連するワードを色々検索してみるのも良いです。
筆者の場合は、先の例で、「山田〇〇+詐欺」ではなく、「田中〇〇+詐欺」と検索したら黒い情報が出てきたこともあります。
さすがに、エゴサーチもせずコンタクトしてくる人は、詐欺師の中でもグレードが低い?詰めの甘さですが、あらゆる方法で個人情報を調べにいくことをおすすめします。
保証・担保周りを気にしてくる
近年のM&A詐欺でよくある手口は、M&Aで買収した後現金だけ抜いてトンズラする、という手法ですが、ここで重要になってくるのが金融機関の個人保証・担保周りです。
詐欺に遭う売主の共通点は、保証や担保を外していないのに株や銀行口座や印鑑を渡してしまい好き放題される、という点ですので、裏を返せば、株や銀行口座や印鑑を渡す前に保証や担保を外すか買手に付け替える手続きを金融機関も交えてしていれば被害に遭う確率がグッと減ります。
なので、詐欺師が狙いやすい案件というのは、「借入金が無保証・無担保である」や「借入金の保証や担保を抜く前にM&Aを実行してくれる相手である」という会社になるわけです。
交渉相手が「会ったばかりなのにやたらと保証とか担保周りのことを聞いてくる」とか「金融機関関連の契約書類だけ依頼が細かい」と感じたら、少し疑ってみるのも良いでしょう。
ちゃんとした買手もこの辺は確認してから買収しますが、実際のところ最初の段階でここだけ焦点を当てて根ほり葉ほり聞いたりはしないものです。保証や担保は元になる債務を返済してしまえば消えるものなので、借金を返してしまえば問題ないと考えるためです。
接触経路が買手から
M&A詐欺は基本的には買手側(詐欺師)からのコンタクトによってやり取りが開始します。
筆者の場合も、怪しい買手から買収のオファーは全てM&Aプラットフォーム経由でした(M&Aプラットフォームが悪いと言いたいわけではなく、仕組み上買手からのアクションが起点になりやすいということです)。
詐欺師は詐欺を働くだけのメリットがある案件か、相手を騙せそうか、を基準にターゲットを選別しますので、例えば、先のような手口であれば、コロナ融資で借入はたくさん起こしているけどただキャッシュを眠らせているだけ、といった案件を狙っていたりします。
詐欺に遭うときは詐欺師の方から近づいてきている、これが鉄則です。
売主の立場であれば、M&Aプラットフォームに登録して買手からオファーを貰う感じで買手探しをする場合は常に警戒しておいた方がよいのと、仲介会社に依頼していてもその仲介会社がM&Aプラットフォームで買手を探しているかを注意しましょう。また、M&A DXの事件でもあった、詐欺を働く買手でM&Aを実行したことがあるから2回目以降は自社の買手ネットワークとして詐欺会社を取り扱う、という事例もあるので、仲介会社がその買手に2回、3回と買収してもらっていたとしても、その買手と仲介会社のファーストコンタクト経路は何だったのか、まで気にした方がよいです。
どういうシナジー効果があるかわかんない
詐欺師がM&Aについてのシナジー効果を説明する時不自然になることが多いです。
例えば、本業が建築系なのに急にアパレル会社を買収するというストーリーにするために、「知り合いがアパレル経営にノウハウがあるから」と、本当にいるか分からない人物を持ち出して説明してくるケースもあれば、「我々は経営のプロだから経営不振の会社であれば業種不問で手掛けている」と、PEファンド風を装ってくるケースもあります。
いずれの場合も、何か証憑に基づいて言ってくるものではないので、「そんなの何とでもいえるじゃん」という内容でツッコミどころもあります。
筆者の感覚的に、M&A詐欺師の場合「買収目的」については事前に結構作り込んでくるケースも多いような印象で、そんなに細かく聞いてもないのに相手から事細かく説明してくる、といった素振りもみられます。
普通の買手であれば、もっと協議しないとシナジー効果あるか分からないですね、といった段階なのに、詐欺師の場合は、事細かく全部知っているかのような確信めいたことを言ってくる、なんてところから何かおかしいぞ、となるわけです。
提示条件が安い
M&Aの提示金額についていえば、詐欺師は「低め」を出してくるケースが多いように筆者は思います。
条件の渋い買手、というのは、詐欺師でなくてもいるので、低いからといって詐欺師という訳では全くないですが、本当にシナジー効果があるような買手と比べると低くなりがちです。
例えば、現金1億円、金融機関借入1億円、純資産5,000万円の黒字企業があったとして、詐欺師は5,000万円(純資産相当)を提示するとします。そうすると、M&A時に5,000万円は支払うものの、現金1億円をトンヅラすれば+5,000万円の儲けになります。もし4,000万円で買収できれば儲けは6,000万円、と安く買収できればできるほど詐欺できる金額が大きくなるのです。
ところが本当にM&Aしたいという買手がいた場合、6,000万円とか7,000万円といったのれんも加味した金額提示になることもあるため、詐欺師が5,000万円を提示したとて買手として売手に選ばれず、M&Aが実現できない(詐欺できない)ということになります。
なので、事業内容がニッチすぎたり、場所が田舎すぎたり、従業員が皆高齢者だったりといった、あまり買手が付かなさそうな案件(M&A業者も買手探しに難儀する案件)を詐欺師は狙いにいくのです。
手練れの詐欺師としては仲介会社の心理も熟知しているので、「早く成約させたい」という担当者の心理を読んで、仲介会社が喜ぶ意向表明書の提出を匂わせて、「売主が納得する最低限の金額」を聞き出し、あとは仲介会社の担当者から第三者のアドバイスの体でゴリ押しさせてM&Aまで至る、というのが、これまで仲介会社に片棒を担がせて詐欺を行う詐欺師の常套手段です。
ただ、先ほどの例で、例えば2億円を提示します、といった買手だったとしてもそれはそれで疑うことを辞めてはいけません。
この場合は、M&Aを成立させてトンズラ、ではなく、そもそもM&A代金を支払わない方法を考えているか、基本合意以降他の買手が降りたのを見計らって値切ってくるか、M&A代金という形でなく、後日退職金を支払うとか役員報酬にするといった支払方法の変更を申し出てくるなどといった点に疑う余地を残しますので。
個人情報について触れると逆上する
詐欺師は個人情報を出したがりません。
なので、本人確認資料を求めたり、何かしらの証憑を求めると逆上することもあります。
余程失礼な聞き方でもしない限り逆上すること自体が怪しいので、筆者はこういう反応が見られた段階で限りなくクロに近い人物として取り扱うようにはしています。
ただ、偽造する、という手段も無くはないので、証憑を提示したからといって安心できるわけではなく、どちらかというと個人情報を求めたときの挙動を見る方が目的な気がします。
買手詐欺に事前に気付くための対策4選
こういった詐欺をする買手に気付くためにはどうしたらいいでしょうか?
完全に防げない可能性もありますが、他にも色々ありますが、少なくともこれらのことをするだけで一定程度詐欺に引っ掛かるリスクを減らすことができるのではないかと思います。
最初に素性を確認する
相手に怪しい素振りがあったとして、途中から「本人確認資料を見せて」とは中々言いにくいところがあります。
なので、最初の段階で「どの買手候補の方にでも念のため確認してまして、」という感じで聞いておきましょう。
この時、メールの文面だけとか、相手方がパワーポイントで作った資料だけ、といったなんとでも作り話のできるものではなく、きちんとした資料(公的証明書など)を貰うようにしてください。会社の謄本ではダメです。
もし、適当にはぐらかそうとしてきたり、逆上したり、M&Aプラットフォームで本人確認してるから、と抵抗してくる場合は少し警戒レベルを上げる方がよいです。
証拠の残るものを入手することで、後々相手方の矛盾を突ける可能性が上がりますし、表面上の会話だけで騙されないタイプの売主だぞと示すことも抑止力に繋がります。
もちろん、本人に聞かずとも相手の素性が調べられる場合はこの限りではありません。
他の候補先がいること、専門家がいることを伝える
前述の通り、もし詐欺師の他に交渉している買手候補がいる場合、詐欺師が売主や仲介会社を巻き込んで詐欺に引きずり込みにくくなります。
また、M&Aに熟知している人間や、弁護士や会計士などの専門家がバックについていると詐欺が見破られる可能性が高まるので、自分から引く可能性も考えられます。
あまり露骨に他の候補先の話ばかりをすると、普通の買手も引いてしまうこともあります(「他が検討されているならウチは後でもいいです」的な)ので、警戒レベルに応じて敢えて強調した伝え方にするなど工夫が必要になります。この匙加減はある程度経験ないと難しいですが。。
過去に買収した会社に行ってみたいという
詐欺の話題でなくともこういう要望を出される売主もたまにいますが、買手が過去に買収した会社に訪問するのも有効な手段です。
詐欺師側として、騙す相手が現地に来る、というのは、大がかりな準備が必要になってくるので、極力避けたいはずです。なので抵抗してくることもあり得ますが、本来普通の買手であれば割と快諾してくれることが多い内容です。普通の買手はM&Aしてから売手にハレーションを起こしてほしくないので、「ウチのグループはこういう雰囲気です、肌に合いますか?」ということはM&A前にむしろ実施しておきたいと思うでしょう。
「なんでそんな依頼してくるの?」と聞かれたら、「同じグループになるイメージが付いていないので、貴社に売却した前のオーナー(子会社の社長)にも話を聞いてみたい」と一点張りすれば大丈夫です。
M&A業者がこういった依頼を渋る時は、単純に面倒なだけが多い気もしますが、買手にそういった依頼ができるような関係性でない場合や訪問されると業者的に困る事情がある?と疑うのが無難でしょう。
詐欺を働くインセンティブを与えない
詐欺をするインセンティブを与えないのも有効な方法の一つです。
例えば、口座からお金を抜く詐欺を目論んでいるのでは、という疑いがあるのであれば、「それができないスキームで進める予定であることを伝える」といったことです。
株式や銀行口座、印鑑を渡した後で保証・担保の変更を金融機関に申し出る、という進め方は詐欺師が喜ぶ方法ですが、一旦全額返済するか金融機関に保証・担保変更の承諾をもらってからでないとM&Aしない、という進め方であれば詐欺師は寄り付かなくなる可能性が上がります。相手が詐欺師でなくて普通の買手だった場合は、こういう進め方だからM&A検討辞めよう、とはならないので、相手の反応で怪しさ度合が判断できる可能性もあります。
一方、シナジー効果については、何とでも言える話題でもあるため、あまり深堀したところでボロが出るかは微妙です。もし、シナジー効果について追及したいのであれば、相手方から出てきた情報の裏取りをしにいくのがよいです(関係会社の〇〇とシナジー効果がある、という話であれば、その関係会社が実在するかどうか、相手方がその関係会社の株主・役員か、相手の言っている取引先と本当に取引しているか、などを謄本や現地確認、外販の企業データベースなどで調べに行くイメージです)
仲介会社も加担する可能性がある点に注意
正直、M&Aをこれから初めてやります、という方がM&A詐欺を見抜けるか、というと難しいと思います。
なぜなら、「他の売手はそんな依頼しないですよ」とか「一般的なM&Aはそんな進め方しません」と言い切られた時に、押し返せるだけの知識や経験が無いからです。
実は、M&A仲介会社が買手によるM&A詐欺に加担してしまうのは、何としてもすぐにM&A成約させたいという動機付けの他、詐欺を行う買手に言い負けてしまっている、ということも考えられます。
最近では、「M&A業者もヤバいんじゃないの」という雰囲気はありますが、これはこれで事実で、経験値が少なかったり、何をしても早く成約させたいという担当者に当たってしまうと、業者が詐欺師を見抜けなかったり、成約欲しさに詐欺師をよい買手として推奨してしまったりして一層詐欺に遭ってしまう可能性が高まります。
違和感を感じたら一旦止める、状況をきちんと整理できる人に相談する。
少し面倒ですが、そうした細かい積み上げで余計なリスクを排除できることもあるので心がけておくようにしましょう。
他にも色々見るべきポイントもありますが、少し長文になってきたので、気になる人は筆者に個別にご相談下さい。最近はなぜかこの手の質問をいただくことが増えていますが、こういう話題は一人で抱え込まない方がよいと思いますので!
最後までお読みいただきありがとうございました。
筆者へのご相談、ご質問については下のお問合せフォームよりお問合せ下さい。
お問合せ