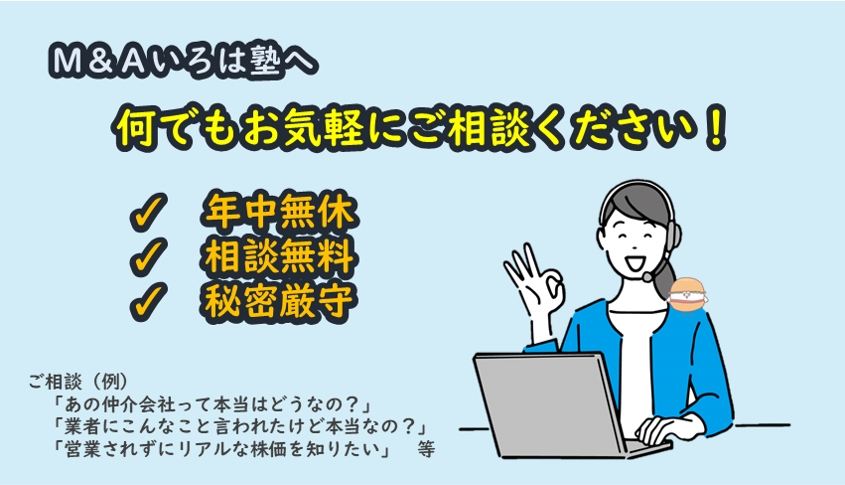お悩み社長
お悩み社長
トミス建設とマイスホールHDのM&Aと、それに関係したとみられるM&A総研について、先月から結構盛り上がりをみせています。
出回っている記事を要約するとこういうことみたいです。
・トミス建設(売手)とマイスHD(買手)の両社とアドバイザリー契約を結んでいた第三者機関「M&A総研」(仲介)が、M&A契約締結直前で8月5日に契約を一方的に解約
・M&A総研担当者は「手数料がかからずラッキー」と発言
・仲介との契約解約するも、トミス建設とマイスHD間では契約締結
・M&A後、トミス建設側からマイスHDへ4,000万円送金、その後数カ月で合計約1億2,039万円が同社や旧代表ら関係先に送られたらしい
・トミス建設前代表は騙されたと憤り、錯誤無効を主張して代表に復帰。給与未払いなど複数の問題も浮上し訴訟へ
・マイスHD側は送金は買収後の資金管理として適法と説明。また、M&A総研から提示されたLBO(レバレッジド・バイアウト)方式による提案に基づく買収計画だったと弁明。M&A総研からの契約解除については、手数料4億円を支払った直後だったことに疑問を呈した
・M&A総研は個別案件について守秘義務を理由にコメントを拒否
トミス建設はマイスHDを訴えて、マイスHDは弁明しつつ、今回の騒動でM&A総研が関与を認めないのはおかしいといい、M&A総研はコメント拒否、という構図なのでしょうか。
M&A業界ではルシアン事件のような詐欺事件も発生しているのでタイミング的には盛り上がりやすい内容ではありますが、今回はマイスHDも会社HPに正式コメントを出していたり裁判を通じて明らかにする旨を公表しているので、いきなりルシアン事件と同じ論調で取り上げられるのはちょっと違うかなと思いますが、真実は法廷で明らかになっていくのでしょう。
あとは、M&A総研の対応についても問題が無かったのかという声もあるようです。
確かにM&A契約締結直前にアドバイザリー契約を仲介会社側から解除するなんてことは普通しないですし、M&A総研担当者の発言からこのM&AにおいてM&A総研は成功報酬を受け取っていないようにも読めるので、M&A総研が成功報酬を投げ出してまでこのM&A案件に関与しないようにした理由があったのでは、と同業者なら普通思うところではないかと思います。
とはいえ、最終契約直前でアドバイザリー契約を解除したとしても全くそのM&Aに関与していなかったというわけにはならないと思うので、「そもそもトミス建設とマイスHDのM&Aに問題があったか」「仲介会社はそこにどう関与したのか」はM&A業界的にも明らかになった方が良いと思います。
詳細は筆者も分からないので憶測で話をすることは避けますが、こういう話があると、これから会社を売却する売主が「LBOはヤバいスキームだ」となりそうな気もしますがそういうわけではありません。
LBOについては、M&Aで会社を売ろうとしている方にも正確に理解しておいてほしいので、今回はM&Aの売手目線でどう考えたらいいのかをお伝えしていきたいと思います。
そもそもLBOスキームとは
そもそもLBOスキームとは何か、簡単に分かり易く整理しましょう。
LBOとは、会社を買収する際のお金の集め方の方法の一つで、自己資金だけではなく、買収資金を金融機関融資など外部資金を利用することで確保する方法です。
タイトルの事件でもLBOスキームが話題になっていますが、これは買収した会社の資金を利用して、また、新しい会社を買収するという方法なのですが、これも広義にはLBOスキームといわれます。
定義としては、資金源について「買収資金の一部又は全部が借入金(レバレッジ)で調達されていること」、返済原資について「買収対象企業の将来キャッシュフローや資産から行われる前提であること」という条件を満たせば、LBOと理解しておくとよいでしょう。
こんなLBOですが、感覚的に、どこからからお金を借りてきて、もし買収した会社の運営が上手くいかなかったらどうなるの?と思う方も多いと思います。
これは実際その通りで、普通の会社は業績が日々変動するので、買収したはいいものの業績が悪化して返済原資が無くなってしまう、ということも起こり得ます。
買手がM&Aで買収する際に、楽観的なバリュエーションで高値掴みをしてしまうこともM&Aの現場ではしばしばありますが、どのくらいのキャッシュフローを生み出すかについては保守的に見ないとリスクの大きいスキームでもあります(というか、あまりに無茶な計画だと融資が組めません)。
一方で、LBOスキームでは買手側がM&Aの際たくさんの自己資金を必要としないので、自己資金だけでは1社しか買収できないのに、例えば2社、3社と買収することができたりします。投資効率を上げるために利用されるスキームでもあるので、スピーディに事業規模を拡大できるメリットもあります。LBOスキーム自体は別に違法なスキームでもないですし、投資を専業にするPFファンドなどはよく使うスキームでもあります。
要はプロが上手く使えば買手にとっては有用なテクニックってことです。
あと、極端な話をすれば、内部留保をためまくっている会社を割安で買う、具体的には、PBR=1未満で会社を買う(会社の解散価値よりも低く買収する)ということができるなら、LBOで手出しゼロで買収し、買収した会社の内部留保から返済分を吸い取り、残った資産を自分(買手)のものにしてしまう、なんてことも出来はします。売買金額は当事者で決められるわけですので。
これは違法ってわけではないですが、明らかに道義的にどうなん?って言われる話で、少なくともM&Aの売手としては良い気持ちはしないでしょう。
上場会社でもない、譲渡制限のある会社であれば、見ず知らずの会社にいきなり株を買われるということはないですが、中小企業M&Aでも無関係ではないです。例えば、買手に「あまり高い金額では買収できないけど、会社と従業員を守ります」と感情に訴えかけてこられたから安く譲渡したのに、M&A後はろくにまともな企業運営をせず、お金を引っ張るだけ引っ張ってあとは会社を精算される(当然、従業員も解雇される)という話なわけですから、売手としては「騙された!」という感情にもなるでしょう。
内部留保をためておくというのは企業にとって重要ではありますが、悪意のある会社に標的にされて言葉巧みに近づいてこられると危険でもあるということなのです。
LBOスキームを使う買手との取引はデメリットしかない?
筆者がもしM&Aの売手の立場だったら、買手がLBOスキームで買収したい、と言ってきたら正直面倒だな、と思ってしまいます。
買手がどうやって買収資金を調達してくるか、という話なので、一見すると売手には関係のない話のように思いますが、実際そうではないからです。
むしろ売手としてはデメリットしかなくない?って話なので、筆者なら自己資金で気持ちよくスパーンと買ってくれる会社に売却しますね。
では具体的にどんなデメリットがあるか挙げてみますので、イメージしてみてください(筆者の主観も含むのであしからず)。
資金余力のない買手なのかもしれない
M&Aする段階から借入をする会社というのは、そもそも自己資金が無いか、あるいは、手元資金をあまり出さず最大限レバレッジを掛けてM&Aに取り組む会社ということになります。
M&Aで売却する先の買手というのは、買収の時だけお金があれば良いというものでもなく、買収後も資金需要が出た時に支援できる余力があるかも当然重要になってきますが、買収の時から借入を起こすというのは資金余力の観点で不安に感じる売手もいると思います。
不動産投資などでよくレバレッジを最大限活用して、買った不動産に担保を付けて借入を起こして新しい不動産を買う、みたいなやり方もありますが、筆者は超安定志向なので「そんなに借入漬けになって大丈夫かな」と思ったりします。不動産業界の人にいわせれば融資は引けるだけ引くみたいな発想もあったりするので、結構感覚が違うものだなと思います。
どっちが正しいという話でもないですが、特に企業買収の場合は、投資としては不動産よりももっとボラティリティが高く不安定なので、「本業がしっかり利益を出している会社に、自己資金で買ってもらう」というのが資金余力の点で安定していることはいうまでもありません。
M&Aするのに時間がかかる
外部から資金調達をする場合、自己資金で買収をするのと比べて買手側の時間がかかります。売手としては待たされるということです。
銀行から借入する際には、買手で作成しないといけない資料も含めた様々な資料提出もありますし、買収する会社の将来キャッシュフローの想定や買収金額の妥当性等をきちんとした買収監査(デューデリジェンス)を基に説明しないといけません。銀行側の手続きとしても、与信の調査や稟議を通す作業もあります。
これが100%自己資金で買収する買手なのであれば金融機関周りの交渉は省けるので、とってもスピーディです。
売主に健康不安があるとか、早期に経営支援してほしいとか、売主がM&Aのことを考え始めると事業に対するモチベーションが下がるので早く売りたい、といった事情があるならなおさら早くクロージングを迎えたいと思いますので、あまり複雑なスキームを考えている買手を選ぶのはフラストレーションが溜まる原因でもあります。
最終契約書で停止条件を付けられる可能性がある
さらに、M&Aの買手が融資で買収資金を調達するような時には、売手と買手との最終契約書のやりとりで、停止条件(ファイナンス・アウト条項)を買手が要求してくることもあります。
この取決めって何かというと、売手が「最終契約も結んで、あとは株式を譲渡するクロージング日を待つだけだな」と思っているところで、急に買手から「融資おりなかったんでM&Aを白紙にします」といわれてしまう怖い条件なのです。
もし、M&Aすることを従業員にすでに伝えてしまっていたなら最悪ですよね。
(普通の仲介会社はこういうリスクを踏まえて従業員開示のタイミングはアドバイスするものですが、過去何もアドバイスしない・間違ったアドバイスをする仲介もいたので注意です)
もっと最悪なのは、例えば上場仲介会社でよく採用されている「仲介手数料の成功報酬は最終契約締結時に支払義務が発生する」という仲介契約を結んでいるときです。
こういう地獄に陥るリスクもあります。
・ファイナンス・アウト条項付の最終契約を売手と買手間で締結
・仲介会社への成功報酬支払義務発生
・その後融資がおりずM&Aが白紙になる旨買手から売手に一方的に通知
・成功報酬の支払義務だけ残る
筆者が売主ならそもそも最終契約締結を成功報酬支払のトリガーにするような仲介会社には依頼しないですが、万一、既に締結してしまっているなら最終契約締結時点で仲介会社とも交渉してクロージング時の費用発生にするか、買手にリバース・ブレークアップ・フィー(簡単に言うと買手の都合で白紙にする時に違約金払えという取決め)等も規程してもらうか、しておいたほうがよいと思います。
どうしても短期的な目線で運営される可能性がある
LBOローンでよく論点になるのが、コベナンツという業績・財務制限条項です。
これは簡単にいうと、例えば「2年間経常赤字出したら貸してるお金全部返してね」というような金融機関との取決めです。
これがあると買手としては「絶対経常赤字出せない」という心理的な負荷にはなるので、業績を上げようという前向きなエネルギーにはなり得ますが、一方でコストカットなども積極的に行うリスクもあります。
もし会社に残してきた従業員の給与も上がらない、といったことが買手による短期的な目線での経営が原因なのであれば、果たして従業員のためになるM&Aだったのかとも思うかもしれませんね。
よくわからない会社の借金を背負わされる可能性がある
買手がLBOスキームで買収を繰り返している会社の場合、自分が売却した会社も他の会社を買収するための財布として使われる可能性があります。
経営権を渡すということは、会社のお金を自由に使わせるということですし、会社の大事な資産を自由に処分されるということです。
そもそもLBOスキームを容認できる買手というのは、1つ1つの企業単体ではなく、企業グループ全体をみて資金配分をする可能性もあるため、売却した会社の今後の維持発展のために蓄積した内部留保だったとしても、その通りになるとは限りません。
それに、グループ内で金銭貸借が盛んにおこなわれると、1社の業績悪化による破綻や支払能力低下が他のグループ企業に波及することもあるため、売却した会社は全然順調なのにとばっちりを受けて財務が急に悪化するということもあるでしょう。
売主としては会社を売却するときにお金を受け取ることができ、その後売った会社が借金を背負おうがどうしようが関係ないというドライな見方もできますが、会社をもっと成長させてほしいから売却したという売主にとっては、売却した会社の成長とは無関係なところにお金が使われているなら本望ではないということになるかもしれません。
買手の資金力・買収資金の調達方法は確認した?
昨今は以前このような記事で紹介した、買手がM&A後売手企業のお金を吸い上げてトンズラする詐欺事件もあったりとM&A業界は荒れまくっているので中小企業M&Aに関するガイドラインも強化されました。
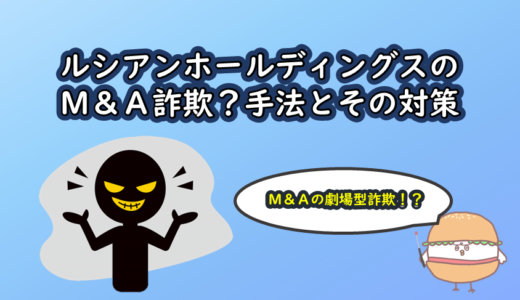 ルシアンホールディングスのM&A詐欺?手法とその対策
ルシアンホールディングスのM&A詐欺?手法とその対策
このガイドラインの中で、M&Aに関わる仲介者・FAは、買手企業に対する調査をしないといけないことになっています。
決算公告や税務申告書を確認して実際に買収できるような買手なのか、もっと具体的にいえば、現預金はあるか、債務超過・赤字ではないか、といった財務的な内容もあれば、反社ではないか、過去M&Aでトラブルを起こしていないか、事業実態があるか、といった様々な側面から、買手にふさわしいかの調査をします。
当然、買収資金はどこからどうやって調達するのかも把握するため、前述のようなLBOスキームの可能性についてはM&Aをする前に売手も知ることができます。
とはいえ、もし仲介者・FAもグルだった場合は売手が被害に遭う可能性もあるので、不審な素振り(やたらと特定の買手を推奨してくる、仲介契約締結前までにこういった調査の存在を伝えない、話しててどうも買手よりの発言が多い、など)が見られた場合は、他のM&A専門家に相談するなど警戒レベルを上げた方が良いでしょう。
そもそも、これまでのM&A業界で起きている事件や不正というのは、往々にして仲介者やFAが成果欲しさに悪に手を染めるというのが原因だったことも多いですからね。簡単に信用しちゃいけません。
また、もし仲介者・FAを使わずに直接買手と交渉するのであれば、ガイドラインも確認しつつ、不明な点は買手に都度確認するようにしましょう。
直接交渉で難しいのは、そもそも相手が何を狙っているかの想像がつかないことや、M&A経験が無い売手の場合買手に「これがM&Aでは普通ですよ」と押し返された時に切り返せないことがあると思います。この辺は、スポットでもよいので、知見のある専門家にアドバイスをもらう方が結果安いと思います。
いかがでしたでしょうか?
結論としては、買手がどうやってお金を集めて買収するのかは事前に確認して、自分や譲渡する会社への影響を考えて行動しましょう、ということです。
担当している仲介者が「この買手なら大丈夫です!」といっても簡単に信じてはいけません、
仲介者は成約すれば大金が入ってくるので変なバイアスはかかっているかもしれないからです。
いつでも自分も騙される可能性がある、と思っているくらいが丁度よいでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。
筆者は金儲け主義のM&A仲介に対してはアンチのポジションなので、結構好き勝手に発言していますが、売主に対しては正直な意見だと感謝されることも多いです。
気になることがあれば下のお問合せフォームよりお問合せ下さい。