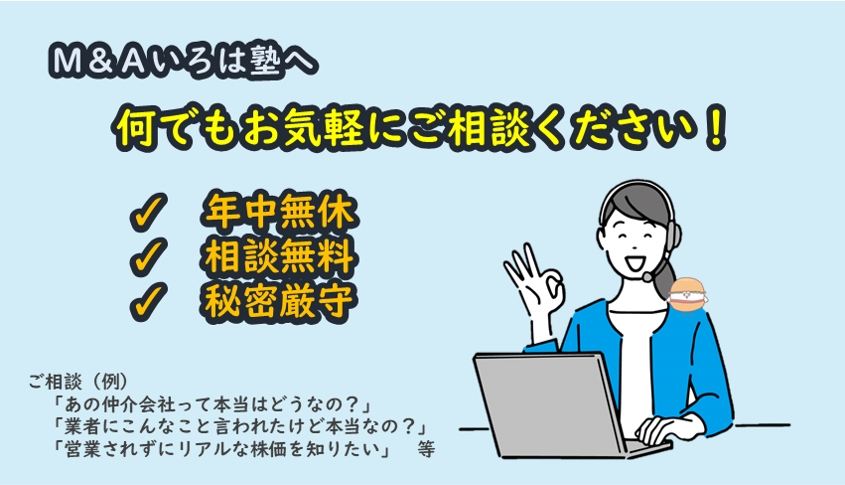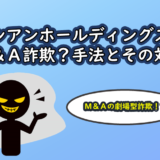最近では会社名も明示された上でM&A仲介会社の不適切な営業活動等が明るみになってきています。
最近報道されているM&A総合研究所についていえば、一部報道で、「資本提携に関するご面談の依頼」と題するダイレクトメッセージを郵送し、実態のない架空の資本提携先の斡旋が行われている可能性があると指摘されています。
こうした類のDMは色々なM&A仲介会社で行われていますが、筆者としてはこちらの記事でもあるように2020年1月からずーっと仲介会社のDMには気を付けましょう、と言っている立場であるので、なんだか今更感はあったりします。
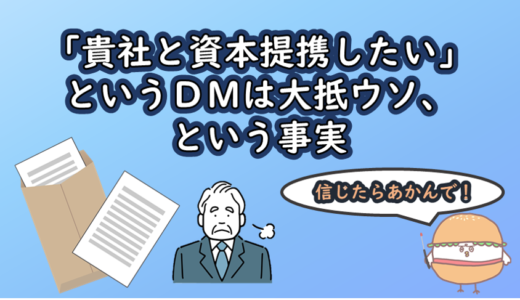 「貴社と資本提携したい」というDMは大抵ウソ、という事実
「貴社と資本提携したい」というDMは大抵ウソ、という事実
ただ、ここにきて社名付きで色々と表に出てきたという感じでしょうか。M&A総合研究所の「買手います営業」についてはかなり前から広く行われており、筆者にも多数相談が来ています。
ちなみに、M&A総合研究所に関する手数料水準等の説明についてはこちらの記事でまとめていますので、こちらをご参考ください。
 「M&A総合研究所はどうして利益率が高いの?」本当の仲介手数料負担についても解説
「M&A総合研究所はどうして利益率が高いの?」本当の仲介手数料負担についても解説
ウソDMありきのビジネスモデルが厳しくなってきた背景
今回はM&A総合研究所のDMについて話題になっていますが、問題になっているウソDMは色々な仲介会社で広く導入されています。
実際にそういったDMを信じて仲介会社と面談した売主がいたのですが、そこで聞いた買手がたまたま知っている会社だったため事実確認したところ、そのような買収提案はしていないという裏が取れているものもあります。
M&Aの「ウソDM」とは、要は、M&A仲介会社が、買手もいないのに「買手がいるので会社を売ってみませんか?」などと中小企業にけしかけて仲介契約を取りにいく、という手法です。
以前こちらの本でも細かく解説しましたが、まだまだ世の中には存在するようです。
 【お知らせ】「M&A仲介会社からの手紙は今すぐ捨てなさい」を出版しました
【お知らせ】「M&A仲介会社からの手紙は今すぐ捨てなさい」を出版しました
この営業の起源は定かではありませんが、筆者の知る限り今から7~8年くらい?前にはもうあったような気がします。
なんでこういう営業が批判されながらも無くならないか、というと、まんまと引っかかってしまう売主がたくさんいるからに他なりません。
M&A仲介というのは、売手を見つけ(成約したらいくらもらうという内容も記載された)仲介契約を結び、買手を探し(成約したらいくらもらうという内容も記載された)仲介契約を結び、M&Aの成約まで見届けるというビジネスモデルです。
当然、いい案件なら買手探しも容易になり、買手がたくさんいれば高い取引額になりやすいの手数料も高くなる、という関係にあります。それゆえ、M&A仲介は「どれだけ良い売手を探すか」が最重要課題とされて、初期的な営業活動に重きを置かれるようになりました。
M&A仲介会社の中には、税理士事務所や銀行などからの紹介により売手と接点を持つ会社もありますが、成約した際などにそういった紹介者に、成功報酬の一部をバックするという商習慣があるため、M&A仲介会社はできるだけ紹介ルートではなく、直接売手と接点を持つということで利益率を上げる努力をしている、という仲介会社も少なくありません。
その「直接売手と接点を持つ」際に有効な手段となり得るのがこのウソDMです。
いきなり見ず知らずのM&A仲介会社がコンタクトを取る、というのも不自然ですし、如実に返信率が下がるので、「買手がいる」という嘘をでっちあげるのです。
ウソDMを送る仲介会社側としては、「ものすごく追及される話になったら、仲のいい買手に協力してもらってウソを真にしてもらえばいい」とか「中にはごく少量でも本当のオファーを混ぜてこれを証拠として出せばいい」という腹積もりをもちつつ、掲示板に上がる営業電話情報にはすかさず削除要請をかけ一般の人からは見えないようにしてきました。
ただ、近年では世の中的に嘘がバレてきてしまったので、DMの効果も落ちたし、もうやめようという風潮になってきているように思います。さらに2024年10月から郵便代も大幅値上げしてますし。
近年、M&A仲介協会という大手仲介会社中心に倫理観を上げていこう、という取り組みを自主的に作っていますがここでもそういった過剰な営業はやめようという規定も盛り込んでいます。
この自主規制の内容については、今まで積極的に過剰な営業をしてきた張本人である仲介会社が何をいまさら、という感も否めないですが、自らがこういう営業はしないと決めることは、これまでの流れから考えると新しい動きと思います。
手数料をしっかり調べない売主
ウソDMに引っかかってしまう売主は総じて手数料をきちんと調べません。
これ、筆者も本当に不思議なんです。
多分、「どこの仲介会社も売手は成約するまで手数料掛かんないでしょ?」みたいなノリで気軽にM&A検討を始めてしまっていることもあると思います。
仲介業者の手数料は法律によって上限が決まっているわけではないので、業者によっては10倍も手数料が違う、なんてことも冗談でなく普通にあります。
それにも関わらずろくに手数料を調べることなく、「この人は信用できそう」「会社の規模が大きいから大丈夫そう」と先入観で仲介会社を選んでしまいます。
手数料についての事実はこちらの記事でも各社の情報を基に、見抜き方を伝えていますが、こうした情報をきちんと理解している人は少ないと思います。
 「M&A仲介会社の仲介手数料でどこが一番高い?」見極め方についても解説
「M&A仲介会社の仲介手数料でどこが一番高い?」見極め方についても解説
でも、理解しているだけで数千万円もドブに捨てなくてよい、というのも実際あるので、知っておいて損はないと思います。
M&A仲介手数料は仲介会社の規模が大きくなるほど高くなる傾向が見られますが、だからといって大手の仲介会社の方が安全にM&Aができるとは限りません。
社内の体制としては確かに大手の仲介会社の方が整っている感はありますが、仲介会社は規模を大きくする過程で少なからず成果主義を取入れているため、それに付随する問題が量産するのです。
・相手を見つける気が無いのに着手金を貰って受託する
・ネットで見つけてきた素性の知れない買手をお勧めする
・売手が飲む条件を引き下げた見返りに買手から追加のフィーをもらう
・買手を煽りDDを簡略化させようとする
・今期中に成約させるため売手が売り急いでいると嘘をつく
・売手に大きなリスクがある契約書でも注意喚起もせず弁護士に見せることを推奨もしない
など
こんなものでは足りないほど、多くの悪行が存在します。
こうした問題は、仲介会社としての体制云々というより、強烈に成果を求めた結果起きる人災のようなものなので、いくらガイドラインを厳しくしても今後もいたちごっこのように問題が起こるでしょう。
最近では、以下の記事のように、買手が売手に対して詐欺行為を働く、という話題も表沙汰になっていますが、こういった買手を紹介し成約に至っているのは決して小規模仲介会社というわけではないです。
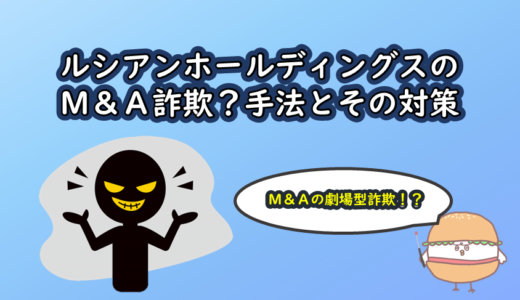 ルシアンホールディングスのM&A詐欺?手法とその対策
ルシアンホールディングスのM&A詐欺?手法とその対策
一部報道による実名公表されている仲介会社は大手仲介会社か大手の関係会社です。つまり、顧客側としては、大手のM&A仲介会社に依頼しても、こうした問題に巻き込まれる可能性があるということです。
確かに、本当にM&Aを依頼できるか怪しい、お金のことしか考えていないヤバい小規模仲介会社がいるのも事実ですが、「小規模=ヤバい」というのは誤解で、むしろ「大手ならちゃんやってくれると思った」という人が最近では詐欺にあっています。ときちんと仲介会社やコンサルタントを見抜く努力をしましょう。
筆者の場合は、そういう過剰な営業が気持ち悪いと思って独立したタイプですので、特にノルマにも追われず丁寧にM&Aを支援していますし、周りにはそういうタイプの小規模仲介会社も多いです。
そうした仲介会社を使った売主は、手数料は大手の半分なのに満足いくM&Aだったと評価してくれることがほとんどです。規模が小さい仲介会社の方が、大きな損害賠償が会社の存続に関わるから保守的に安全に進める傾向があるのかもしれないと筆者は思います。
手数料を規制することで影響が大きいのは大手仲介会社
今後どちらかというとM&A仲介会社への締め付けが強くなるように思いますが、大きな影響が及ぶのは大手仲介会社といえます。当然規制が入れば株価にも影響を与えるでしょう。
理由としては、大手仲介会社の方が、M&Aのディールサイズに関わらず徴収する報酬(≒最低報酬額)が高くなりがちであるという点です。
以下の記事でもお伝えしましたが、仲介会社によって最低報酬額の設定は大きくことなります。
 「M&A手数料って平均はどのくらい?」中央値は500万円という事実
「M&A手数料って平均はどのくらい?」中央値は500万円という事実
今のところ、最低報酬額を規制しよう、という話は出てきていないですが、ここも不動産業の如く業者が徴収できる上限額を法律で決める話になると、当然今までのような利益率は見込めなくなるでしょう。
大手仲介会社から独立した筆者の立場で言えば、「別に仲介会社の規模によってM&Aの進め方が大きく異なることは無いし、大手でも未熟なコンサルタントがいる一方、それよりもずっと優秀なコンサルタントが小規模な会社を経営しているケースも多々あるので、会社の規模に手数料水準が相関している今の現状は逆に不自然」という感想です。法律で最低報酬基準でも作ったらよいと思います。
あと、問題のある業者であれば、大手でもそうでなくとも躊躇なく、M&A登録支援機関の打ち切りや一時資格取消は実施すべきだと思います。そもそもそのためのM&A登録支援制度だと思いますし。変に忖度などせず、中小企業がM&Aをしやすい環境に整えて欲しいなと感じています。
このブログではM&A仲介について、M&A仲介者の立場である筆者の目線で正直ベースでお伝えするものです。内容について共感いただけると嬉しいです。
筆者へのご意見・ご相談等ありましたら下のお問合せフォームよりお問合せ下さい。
お問合せ